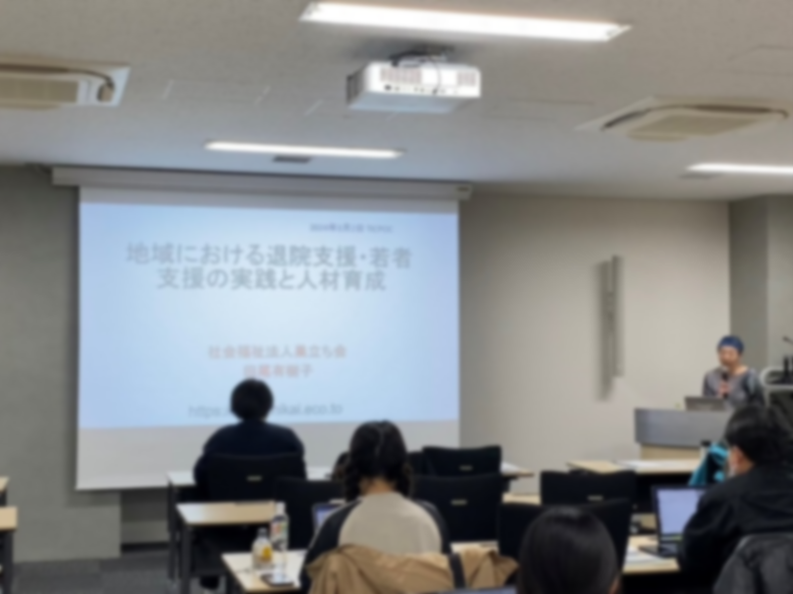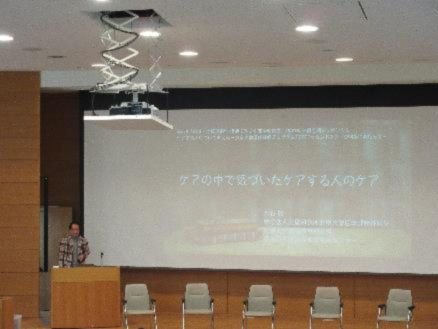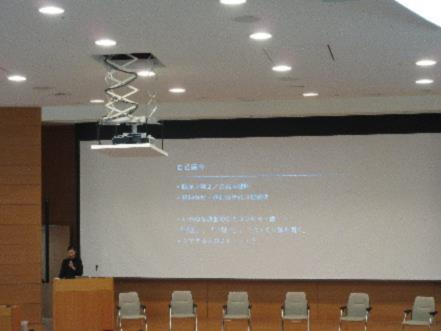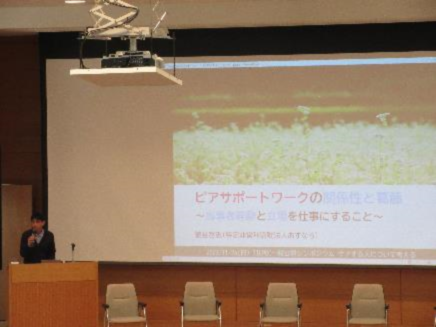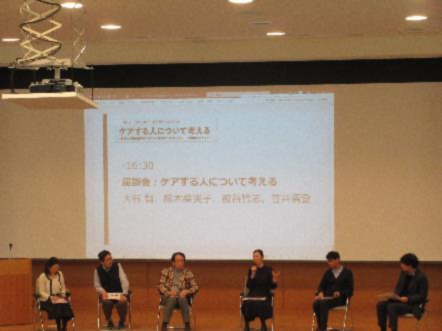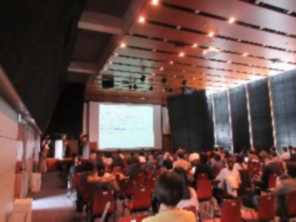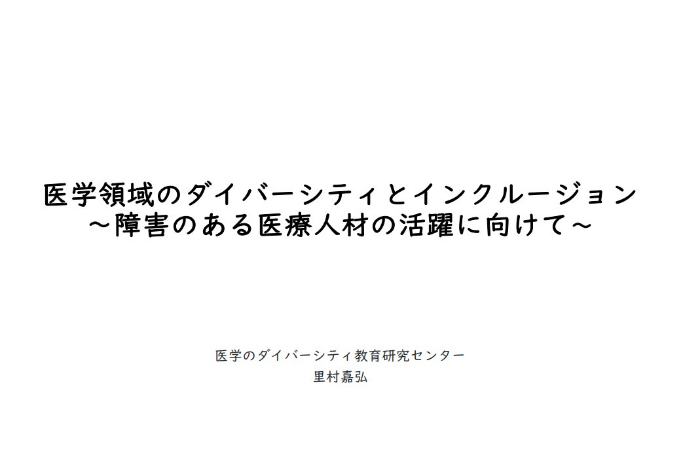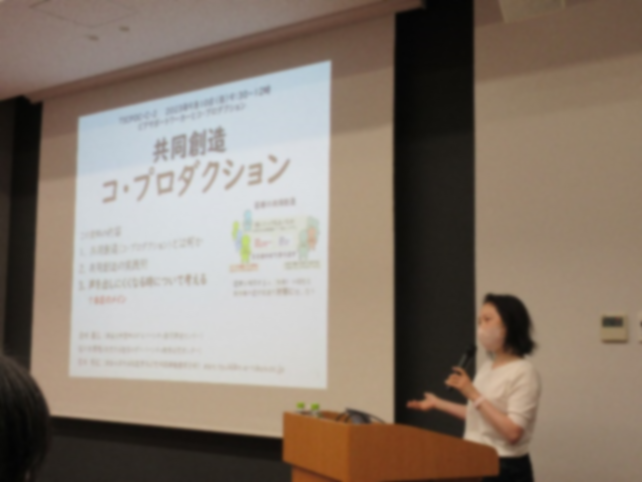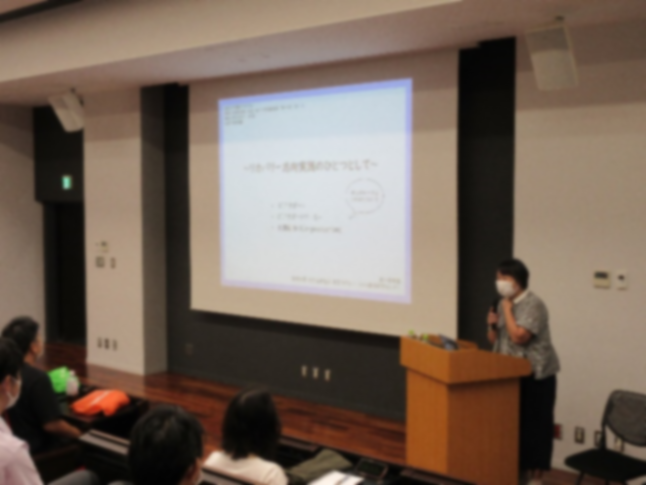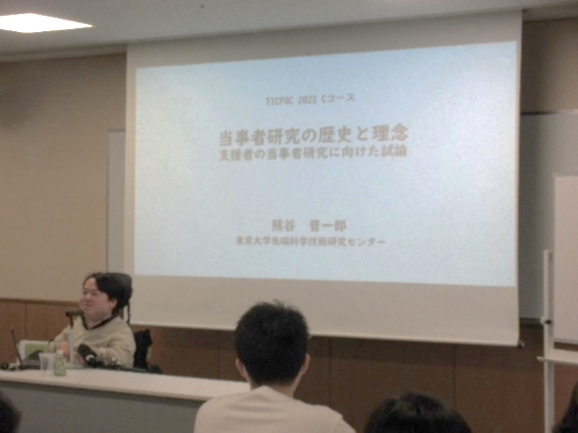Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター
C-2地域連携型コース 3月活動報告
- 日時
- 2024年3月3日(日)
- 方法
- 東京大学本郷キャンパスにて対面開催
概要
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター C-2地域連携型コース3月講義が開催されました。
3月3日午前地域における退院支援・若者支援の実践と人材育成
社会福祉法人巣立ち会 田尾有樹子 理事長
3月3日午後精神障害にも対応した地域包括ケアと意思決定支援(権利擁護と共同意思決定)
国立精神・神経医療研究センター 藤井千代 部長
受講生の感想
(田尾先生の講義)
地域に根差した地道な取り組みと、目の前の患者さんのためにという思いの熱量に大変感銘を受けました。日本の様々な医療・福祉制度の変遷と共に、行政・厚労省の方針や決定にも現場から常に問いかける田尾先生の在り方と物申していくことの大事さを考えさせられました。共生の地域づくりというのは、目標のフレームが先にあるのではなく、日々の、そして長年の地道なやり取りと信頼関係の結果なのだと感じました。
(藤井先生の講義)
地域共生社会の実現に向けての地域包括ケアシステムについて、精神障害の包括的支援マネジメントについて、アドボカシーや意思決定支援について、大変勉強になりました。言葉としては理解できたつもりでいますが、具体的な話としてのイメージがなかなかできないので、これからも学びを続けたいと思います。
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター
C-1職域架橋型コース 2月活動報告
- 日時
- 2024年2月18日(日)
- 方法
- 東京大学本郷キャンパスにて対面開催
概要
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター C-1職域架橋型コース2月講義が開催されました。
2月18日午前臨床心理学の社会論的転回
白金高輪カウンセリングルーム東畑開人 主宰・臨床心理士
2月18日午後スキーマ療法
洗足ストレスコーピング・サポートオフィス 伊藤絵美 所長
受講生の感想
(東畑先生の講義)
臨床心理学の社会論的転回の話で、ユーザー側、社会の側から見るという話について、臨床心理学に限らず、様々な支援サービスにおいても必要な見方だと感じた。また、生存と実存についての考え方についても学ぶことができ、実存の在り方が、文化や生き方にも影響することが学べた。
(伊藤先生の講義)
生きづらさの根っこ(原因)には、早期不適応スキーマがあると考えられ、厳格な条件のもと、スキーマ療法を実施する事により、過去の傷つきに対する修正感情体験を得て、継続的に治療的再養育する事によって、パーソナリティ障害の寛解やパーソナリティやQOLの変容をもたらすと学んだ。過去は変えられないが、過去のトラウマ体験のイメージの書き換えは可能である事に非常に大きな希望を感じた。
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター
C-2地域連携型コース 1月活動報告
- 日時
- 2024年1月21日(日)
- 方法
- 東京大学本郷キャンパスにて対面開催
概要
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター C-2地域連携型コース 1月講義が開催されました。
1月21日午前見えない心を可視化する-心理アセスメントによるケース理解
中村心理療法研究室
治療的アセスメント・アジアパシフィックセンター 中村紀子 臨床心理士
1月21日午後当事者団体の連携協働の事例から-共同創造のすゝめ
精神障害当事者会ポルケ 山田悠平 代表理事
当事者と専門職による協働する 研究・支援の先に見えたもの
国立精神・神経医療研究センター 山口創生 室長
受講生の感想
(中村先生の講義)
見えないものを見えるようにする事は多職種協同の場面でとても有効だし、相談者自身でも説明がつかないような現象を言葉や数値化することで、相談者が納得し主体的に治療に取り組めると思う。支援者も多職種協同することで相談者への理解の幅が広がり、より具体的な支援につながると思う。「あなたはあなたの専門家」という言葉がとても印象に残っている。本人なくして回復はないなと改めて思った。
(山口先生、山田先生の講義)
支援の現場ではまだまだ当事者を抜きにした「支援」が存在します。当事者にただその場に同席していただくことが当事者の参画だと捉えているふしもあります。それに対して違和感を抱く支援者がいないわけではありませんが、「支援者の輪」を優先して、結局当事者の方が我慢するような事態も起こっています。今回の先生方のお話によって当事者と専門職による共同の視点をいただいたことで、まずは違和感を口にして、支援者の輪の中に小石を投げ入れるところから始めたいと思いました。
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター
C-1職域架橋型コース 12月活動報告
- 日時
- 2023年12月17日(日)
- 方法
- 東京大学本郷キャンパスにて対面開催
概要
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター C-1職域架橋型コース 12月講義が開催されました。
12月17日午前精神分析
大正大学心理社会学部 池田暁史 教授
12月17日午後力動的視点を非精神分析的ケア場面に適用する
神戸女学院大学人間科学部 若佐美奈子 准教授
受講生の感想
(池田先生の講義)
これまで精神分析と聞くと、何か難しいものというイメージが強かった。今回の池田先生の講義はとても分かりやすく、フロイトを取り巻く人間関係から精神分析の成り立ちのプロセスについてなど学ぶことができた。
(若佐先生の講義)
支援が困難な患者の支援において、力動的(精神分析的)視点の応用が支援の行き詰まりの突破口になるのではないかと感じた。治療者は患者の内的世界に関心を持ち、語りを聴きながら、ことばにならないものをも聴きとろうと努める姿勢が重要であると学んだ。
第6回公開シンポジウム 活動報告
- 日時
- 2023年11月26日(日)
- 方法
- 東京大学本郷キャンパスにて対面開催(要申込)
概要
2024年度 東京大学履修証明プログラムTICPOCセカンドステージ紹介
笠井 清登(東京大学医学部附属病院精神神経科教授)
ケアの中で気づいたケアする人のケア
大石 智(北里大学医学部精神科学講師)
セラピストとして生き残ること―精神分析とセクシュアリティの観点から
鈴木菜実子(駒澤大学文学部心理学科准教授)
ピアサポートワークの関係性と葛藤~当事者経験と立場を仕事にすること~
彼谷哲志(特定非営利活動法人あすなろ 相談支援専門員)
座談会:ケアする人について考える
大石 智、鈴木菜実子、彼谷哲志、笠井清登
司会(熊倉陽介、宮本有紀)
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター
養成コースC 職域・地域架橋型外部実習 活動報告
- 日時
- 2023年10月29日(日)
- 方法
- 東京大学本郷キャンパスにて対面開催
概要
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター 職域・地域架橋型 外部実習が開催されました。
10月29日午前『多職種協働・若者支援』・グループワーク
東京大学医学部附属病院精神神経科 病棟スタッフ・TICPOC受講生
10月29日午後『多職種協働・地域支援ワークショップ』・総合ディスカッション
JCHO埼玉メディカルセンター 心理療法室 花村温子 先生
むつみホスピタル 理事長 井上秀之 先生
こころのホームクリニック世田谷 院長・理事長 高野洋輔 先生
祐ホームクリニック吾妻橋 院長 夏堀龍暢 先生
受講生の感想
午前
若者支援の最前線で働いておられる先生方がどのような工夫をして支援されているのかを聞けてよかった。学校臨床においては特に、社会における子ども達や学校の状況、元々の学校の風土、地域に応じて自分が専門家としていかに貢献すべきかを考え働くことが必要だと思った。
午後
多職種協働については、「患者さんとの関係性と同様に、他職種に対する敬意を持つこと」ということが強く心に残った。それは、先生方のお話にあったように、抽象的なことではなく、他の職員の方に質問をしたり、他職種の業務について知ることであったり、労働環境を検討したりという、日々の積み重ねから醸成されていくものであると改めて感じた。
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター
Cコース合同 10月活動報告
- 日時
- 2023年10月15日(日)
- 方法
- 東京大学本郷キャンパスにて対面開催
概要
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター Cコース合同 10月講義が開催されました。
10月15日午前精神医学の多元的理解 多職種協働における折衷主義から多元主義へ
京都大学大学院医学研究科 村井俊哉 教授
Values-based practice―価値観の多様性に向きあう実践医療倫理―
東京大学医学部附属病院 榊原英輔 講師
10月15日午後『責任、帰責性、「自己責任」』
東京大学大学院 総合文化研究科・教養学部 國分功一郎 教授
東京大学先端科学技術研究センター 熊谷晋一郎 准教授
受講生の感想
(村井先生、榊原先生の講義)
自分の中の価値が自身の言動や支援にどう表れているかにいかに気づき、価値について思考、言語化していけるかが相手の価値をないがしろにしない支援のために重要であると改めて感じた。気づきのチャンスは支援上だけでなく日々の生活の中にもあり、自分の中の価値を対象化することで、自身の言動をより良い支援につながるよう改めたり、相手の価値を尊重することや変化することにつながると思った。困難ケースにおいては特にコンセンサスが得られないということのコンセンサスを得るということが重要で関係構築のために出発点となることが多いように思うが、そのためにも価値という観点が重要であると感じた。
(國分先生、熊谷先生の講義)
普段考えているようで無自覚だった目的、意志、そして責任について考える機会を頂いた。そして支援の現場における意思決定支援はむしろ、欲望形成支援であり、示唆される事なく、自己責任で突き放される事もなく、安心安全な場でご本人が自分を語り、痛みや弱さを共有できる事が重要であると学んだ。その際、支援者の聴く姿勢が問われると思うし、午前中の講義で学んだ価値の多元主義が通底している事が大変重要だと感じた。
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター
C-2地域連携型コース 9月活動報告
- 日時
- 2023年9月9日(土)、9月10日(日)
- 方法
- 東京大学本郷キャンパスにて対面開催
概要
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター C-2地域連携型コース9月講義が開催されました。
9月9日午後東日本大震災におけるメンタルヘルス
岩手医科大学神経精神科学講座 大塚耕太郎 教授
9月10日午前ピアサポートワーカーとコ・プロダクション
東京大学大学院医学系研究科 宮本有紀 准教授
東京大学医学のダイバーシティ教育研究センター 里村嘉弘 准教授
東京大学医学部附属病院 佐々木理恵 学術専門職員
受講生の感想
(大塚先生の講義)
一時的なケアではなく、継続してケアを提供していくことが大事でもあり、難しい点であると感じた。自身がケアを実践していくだけでなく、地域作りや、関わる人を育てること、またそれらを行うための制度や仕組みを作っていくこと…東日本大震災はまだまだ過去のことではないのだなと感じた。また、災害に関してのみではなく、必要なケアを継続して提供していくのに必要な要素について考えることができた。
(宮本先生、里村先生、佐々木さんの講義)
教育による知識の専門職と、経験による知識のピアサポートワーカーという説明はとても分かりやすい説明で、そこに権威の勾配があってはいけないのですが、専門職間でも権威の勾配があり、声を出しづらい関係があることを日々感じています。コ・プロダクションも支援者と当事者だけの問題ではないのではないかと感じました。今後、自分自身の課題として学びを深めていきたいと思います。
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター
C-1職域架橋型コース 7月活動報告
- 日時
- 2023年7月23日(日)
- 方法
- 東京大学本郷キャンパスにて対面開催
概要
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター C-1職域架橋型コース7月講義が開催されました。
7月23日午前 22q11.2 欠失症候群-重複する障害を抱えた子どもとその家族の生活
22 HEART CLUB のみなさまと
東京大学医学部附属病院22q11.2 欠失症候群メンタルヘルス専門外来担当者
7月23日午後 対人支援関係の倫理的転回~精神分析の視座から
甲南大学文学部 富樫公一教授
受講生の感想
(22 HEART CLUBのみなさまの講義)
今回初めて「22q11.2欠失症候群」について知った。身体・知的・精神の領域にわたる様々な症状、また成長段階による対応や不安の変化といった、患者様・ご家族ともに大変な状況をご家族様より直接伺うことができ、本当に有難く心に響くお話だった。医療の専門性の溝や、18歳の壁、人権への意識、インクルーシブ教育など、多くの課題を教えていただいた。そういったことを治療だけでも大変な患者様・ご家族に担わせず、より仕組みを変えていく方法について考えさせられた。
(富樫先生の講義)
富樫先生が精神分析の内側から、倫理的転回や専門職の加害性や苦悩についてお話くださる中で、専門職がいかに守られ、目の前の方とただの人間として共にいることが難しくなるのかを振り返りました。また、教育の場においても同様で、権力格差がある状況での人間の支配欲と、それに対してどう構造的に是正する必要があるか考えていきたいと思いました。専門職自身が脆弱性も含めて安心して開示出来るような場や職場環境、ただの人間としての自己の回復の大切さも感じました。
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター
C-2地域連携型コース 6月活動報告
- 日時
- 2023年6月18日(日)
- 方法
- 東京大学本郷キャンパスにて対面開催
概要
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター C-2地域連携型コース6月講義が開催されました。
6月18日午前 被害者支援~TICに基づく支援と支援者支援~
被害者支援都民センター 鶴田信子 相談担当心理責任者
6月18日午後 薬物依存症をもつ人を地域で支える
国立精神・神経医療研究センター 松本俊彦 部長
受講生の感想
(鶴田先生の講義)
事件・事故の被害者支援においても通底するトラウマインフォームドケアについて、更に理解を深める事ができた。目の前の傷ついている方、その方の持つ力を信じて、お傍に居続ける事が支援の基本姿勢であると伺い、私自身の対人支援の原点を再認識させて頂いた。支援者の安全安心を守るためには仲間の存在が一番であり、共有と共感によるエンパワメントが有効である事も日頃から実感しており、改めて同僚への感謝の気持ちが強まった。
(松本先生の講義)
薬物依存の状態は当の本人の健康や社会生活を損なうことがあるのも確かだが、薬物の使用は同時に自己治療的な意味もあること、快楽のためだけでなく精神的苦痛への対処方としての使用の意味もあること、これらを知ることで随分薬物依存を持つ人への見方が変わった。「ダメ、絶対」に表される外側からの価値判断だけでなく、当事者の視点から見ることで、支援時の声のかけ方が変わったり、より無理のない共通目標が持てるように思う。薬物依存を持つ人も、そうでない周囲の人も双方が受け入れられるハームリダクションを、社会全体ではまだ難しいかもしれないが、日々の支援では心がけて行きたい。
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター
C-1職域架橋型コース 5月活動報告
- 日時
- 2023年5月14日(日)
- 方法
- 東京大学本郷キャンパスにて対面開催
概要
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター C-1職域架橋型コース 5月講義が開催されました。
5月14日午前 患者・家族の言葉からみえてくるがん療養生活
東京女子医科大学神経精神科 赤穂理絵 准教授
5月14日午後 総合病院の心理臨床
国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 舘野由美子 心理部室長臨床心理士/公認心理師
独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 千葉ちよ 臨床心理士/公認心理師
受講生の感想
(赤穂先生の講義)
こころと身体は影響し合うが、かつて身体科ではこころのケアが重要視されて来なかったが、近年リエゾン精神医学が発達し、特にがん医療で先行している事が再確認できた。患者さんやご家族の貴重な言葉をご紹介下さったが、赤穂先生が信頼関係をじっくり築き、丁寧かつ真摯に対話を重ねられた賜物だと強く感じた。退院後通院での抗がん剤治療を行う患者さんや、在宅緩和医療を受ける患者さんが増え、勤務先の薬局でも患者さんと「第二の患者」であるご家族の支援をさせて頂いている。しんどい時に傍に居させて頂く事の難しさと有難さを感じながら、スピリチュアルペインと向き合い、試行錯誤の毎日だが、原点に立ち返らせて頂いた思いである。
(舘野先生、千葉先生の講義)
患者様へのサポートはもちろんですが、組織の集団力動について心理学的な知見から捉え、その点から状況を説明したり状況の改善を提案していくことの重要性を改めて感じるとともに、それに必要な心理学的な知見が自分に不足していることを痛感しました。とても貴重なお話をいただけました。
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター
Cコース合同 4月活動報告
- 日時
- 2023年4月16日(日)
- 方法
- 東京大学本郷キャンパスにて対面開催
概要
Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター Cコース合同 4月講義が開催されました。
4月16日午前 当事者研究の歴史と理念
東京大学先端科学技術研究センター 熊谷晋一郎 准教授
アカデミアにおける共同創造に向けて
東京大学先端科学技術研究センター 綾屋紗月 特任講師
4月16日午後 トラウマインフォームドケア
兵庫県こころのケアセンター 亀岡智美 副センター長兼研究部長
受講生の感想
(熊谷先生・綾屋先生の講義)
自分だけでは表現できないモヤモヤを言葉にして、同じ境遇の人達と共有できるようになるということが今の社会に必要なんだと強く実感しました。言葉では知っていたはずの「社会モデル」が講義後はより明確にイメージできるようになりました。
(亀岡先生の講義)
組織として安全な環境を構築が出来ているか、職場の様子を振り返ってみると、安心して相談してもらえる環境としては万全ではないと感じました。そのため、どうすれば最善に近づけるのか、どのようなことなら出来そうなのか考えていきたいです。また、トラウマインフォームドケアは誰でも行って良いことを学び、私も実践出来る様に研鑽していきたいと考えました。