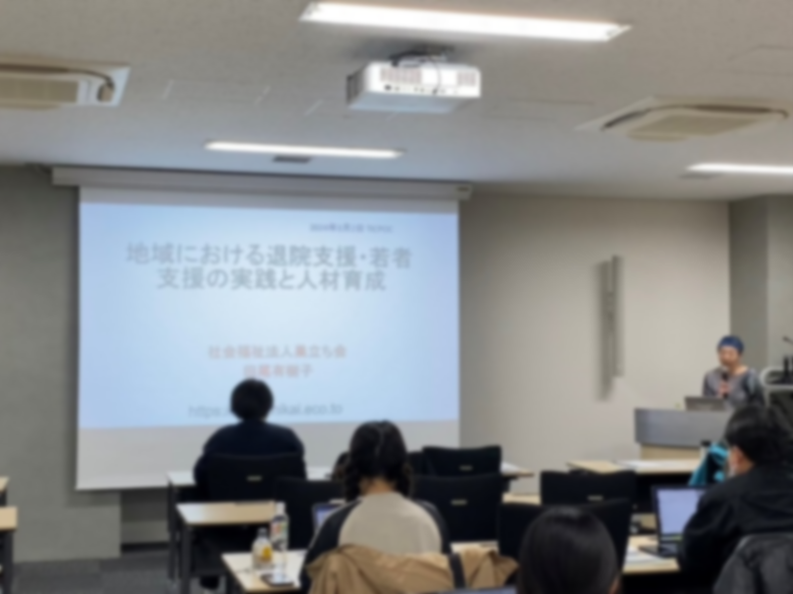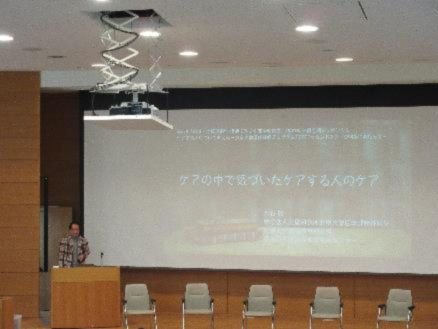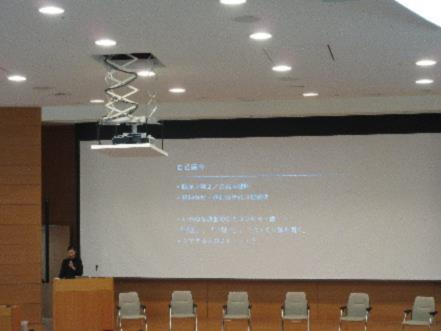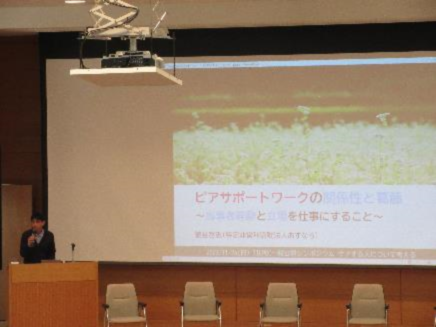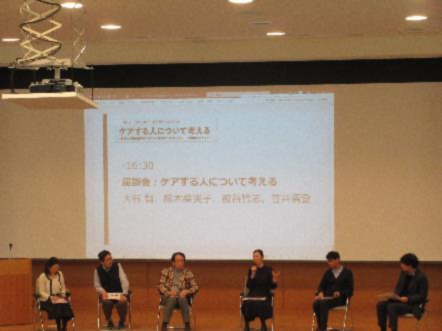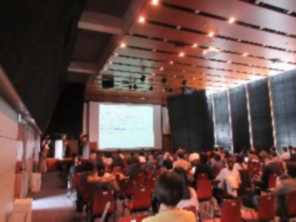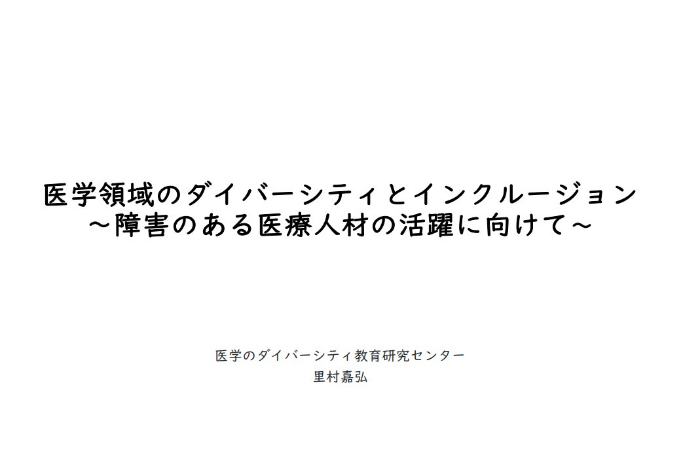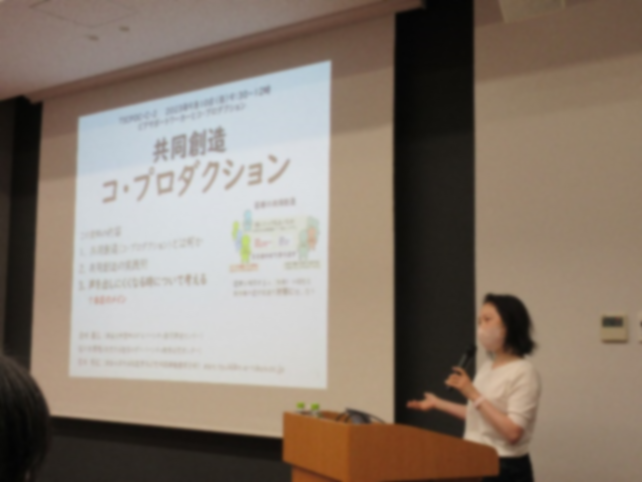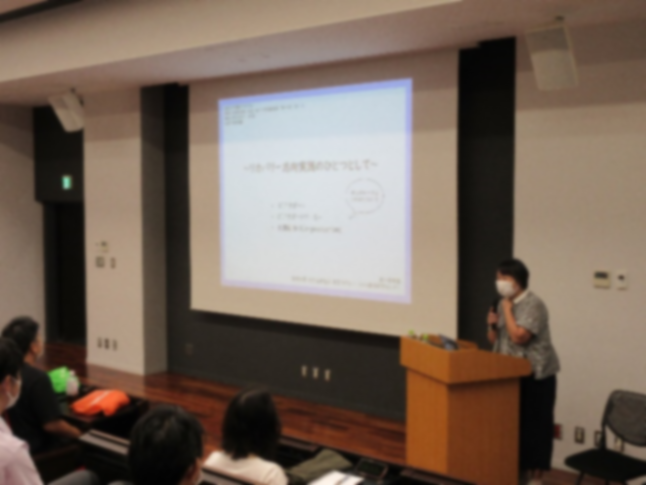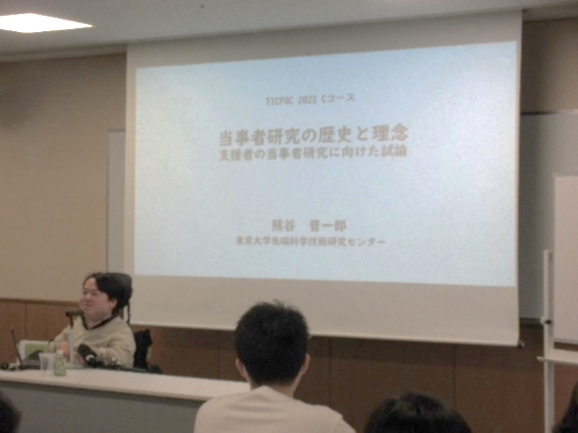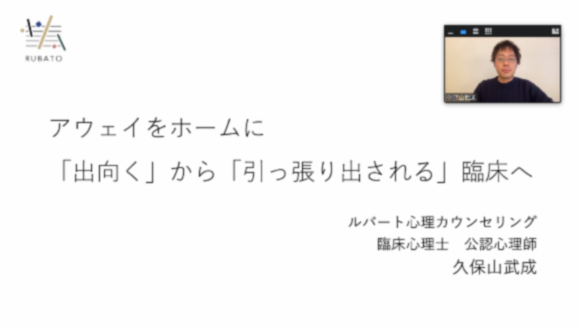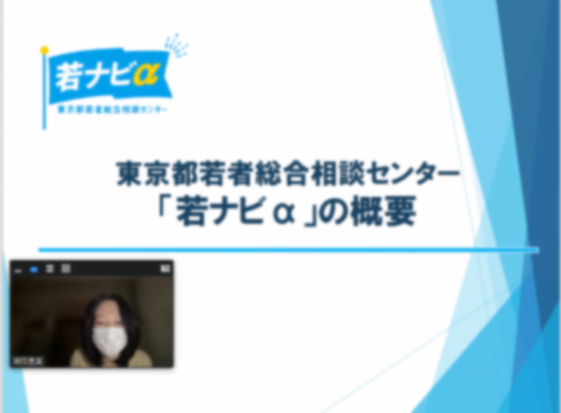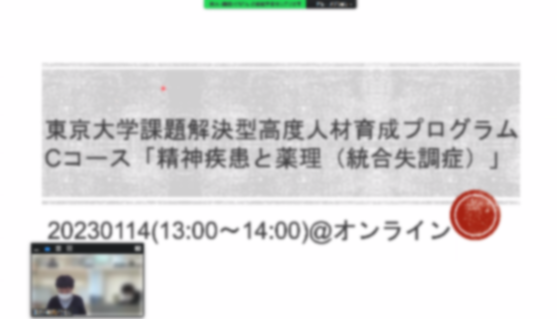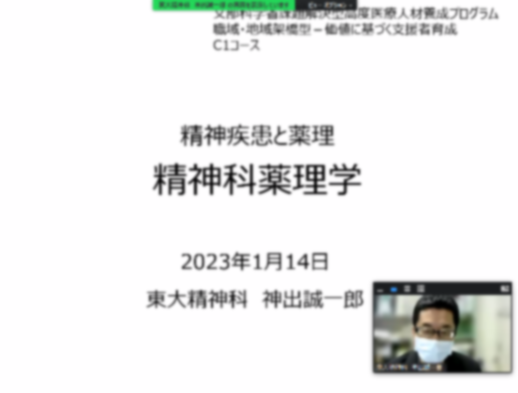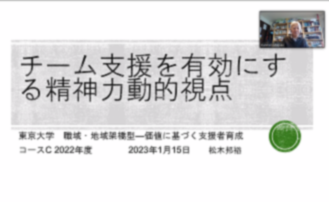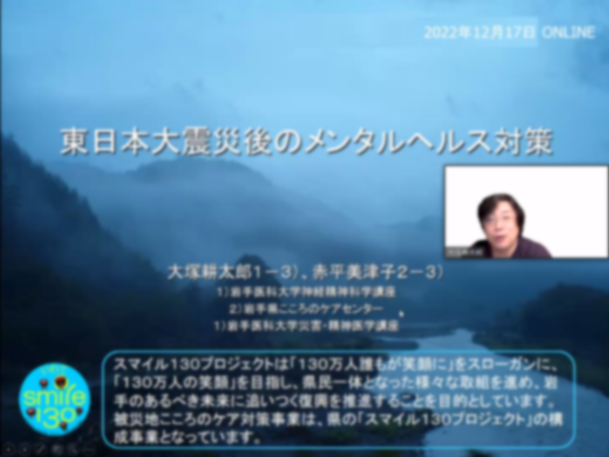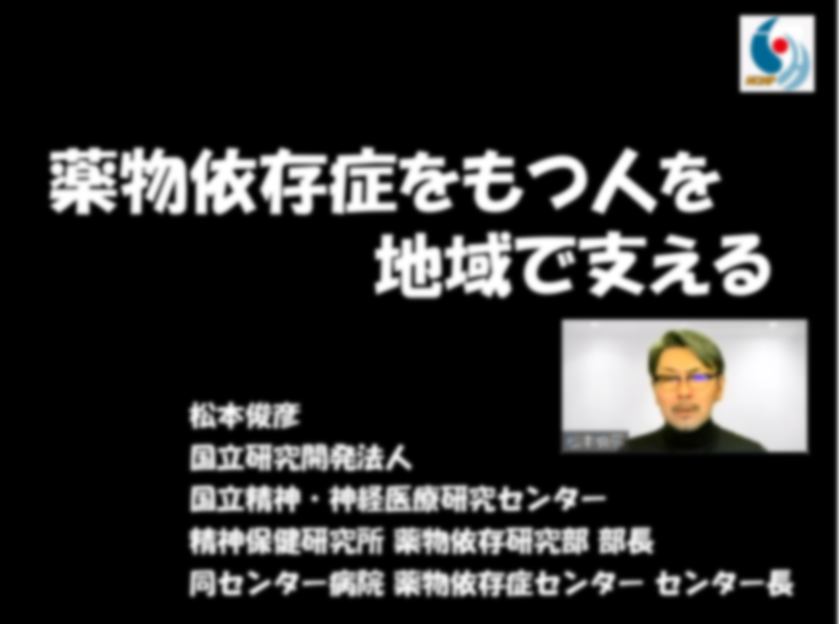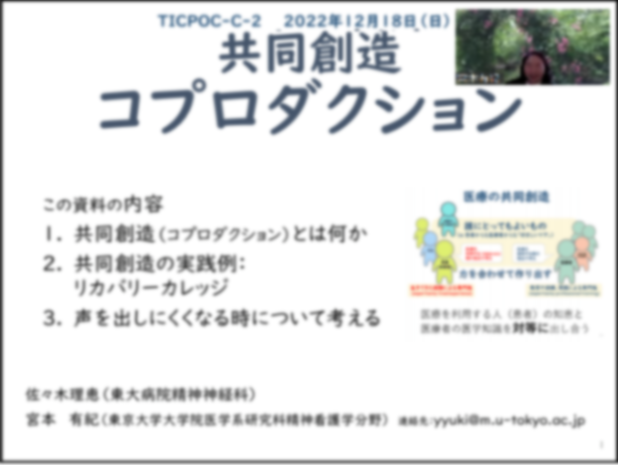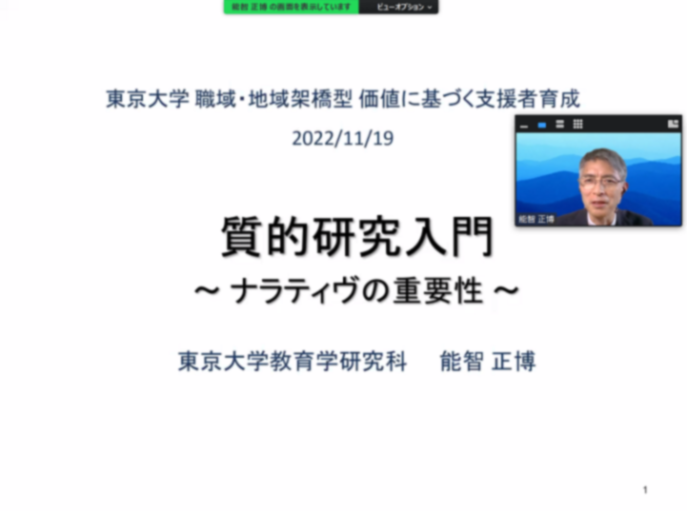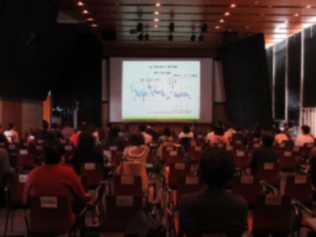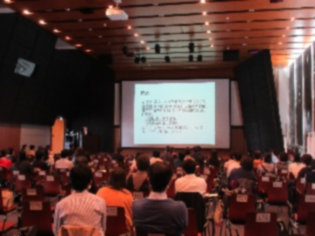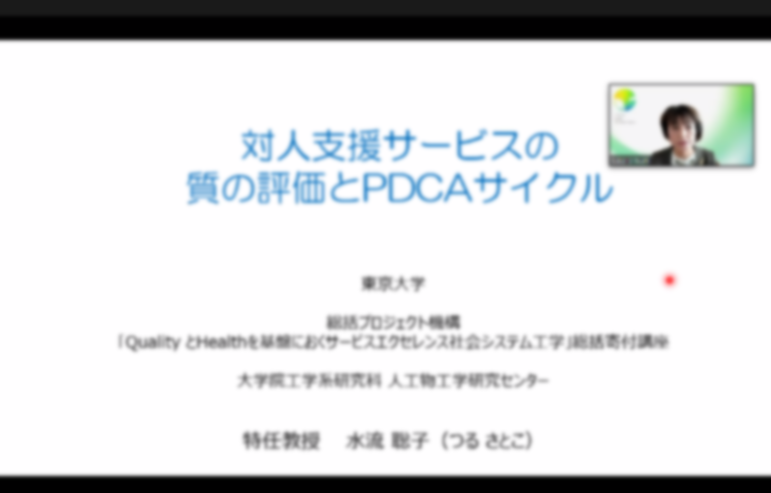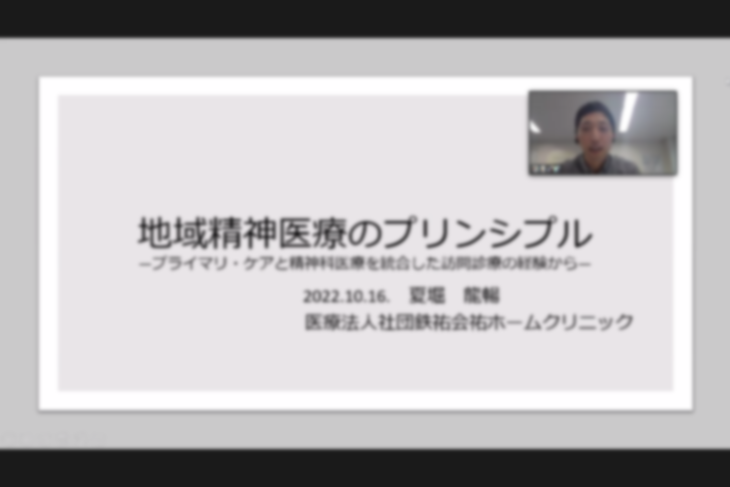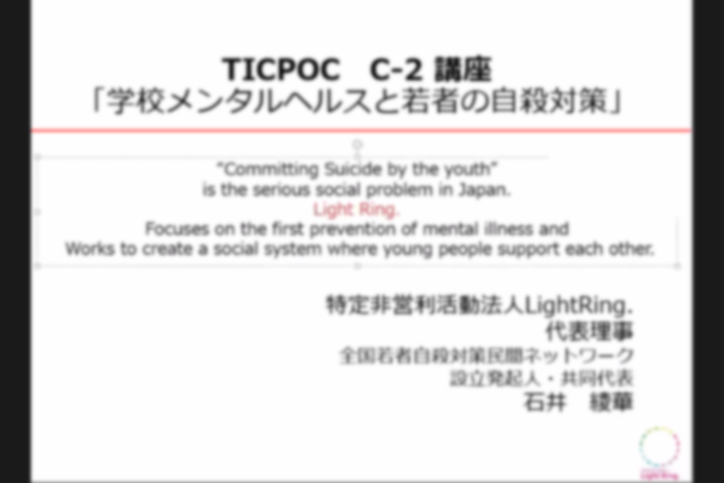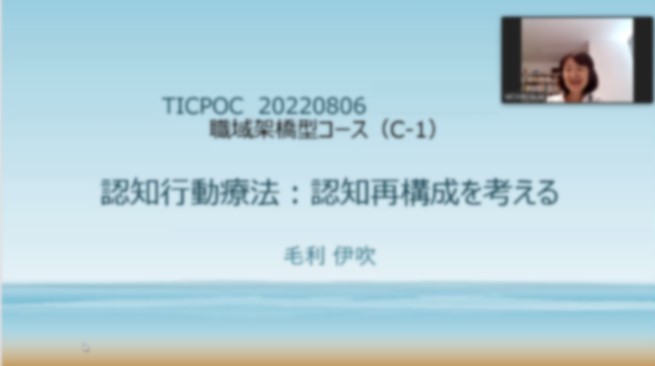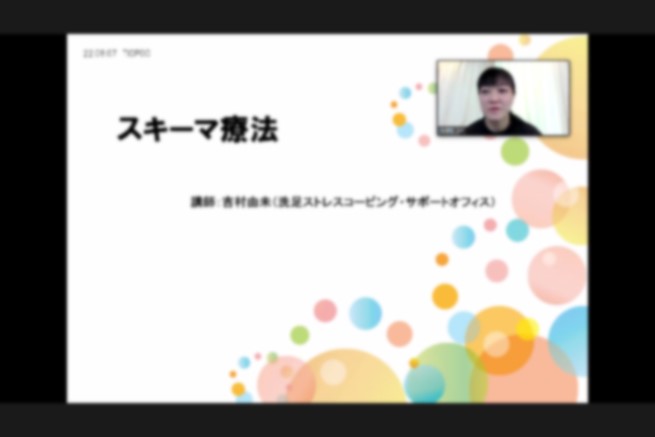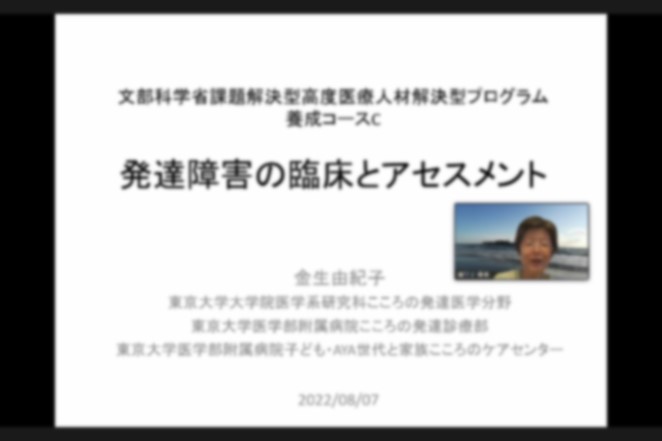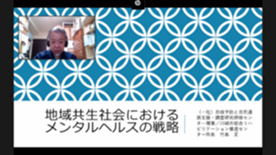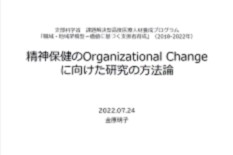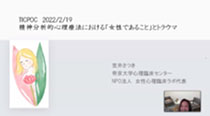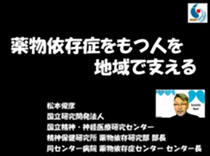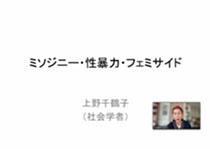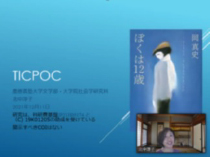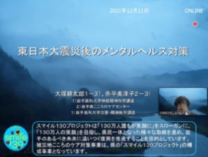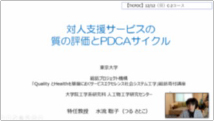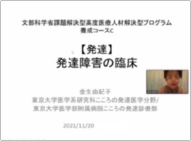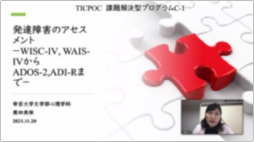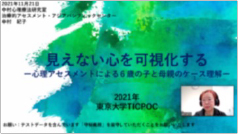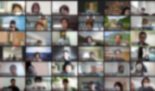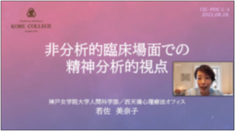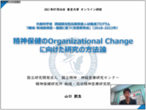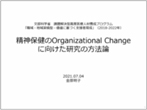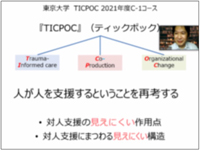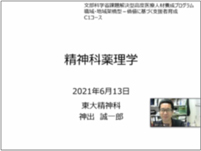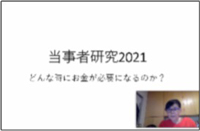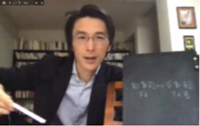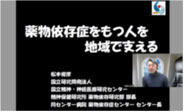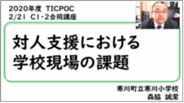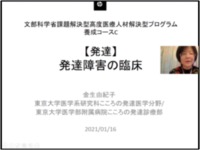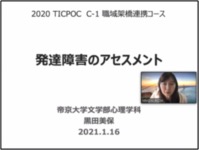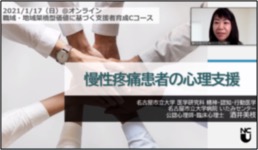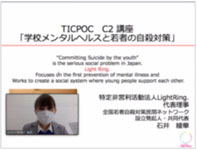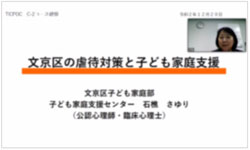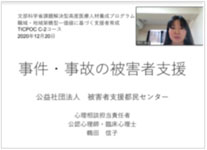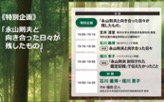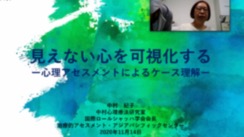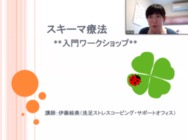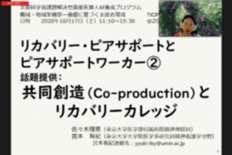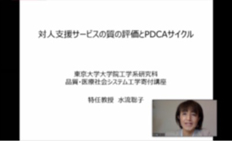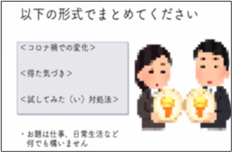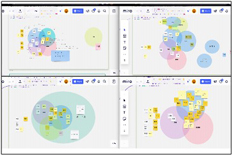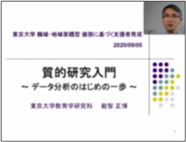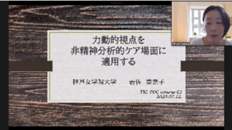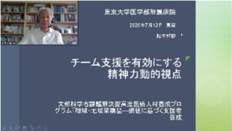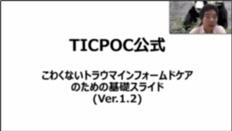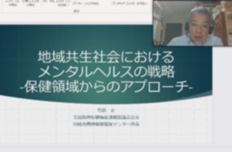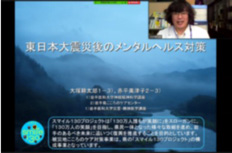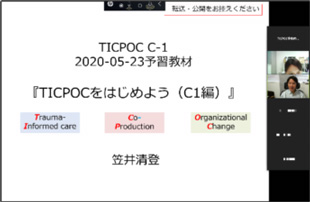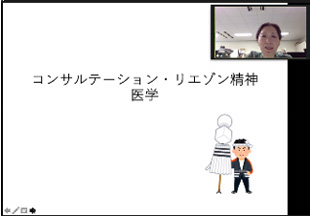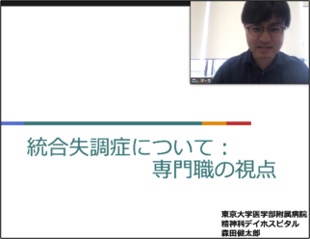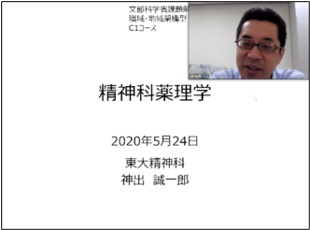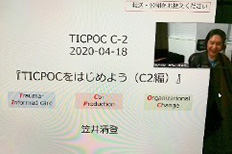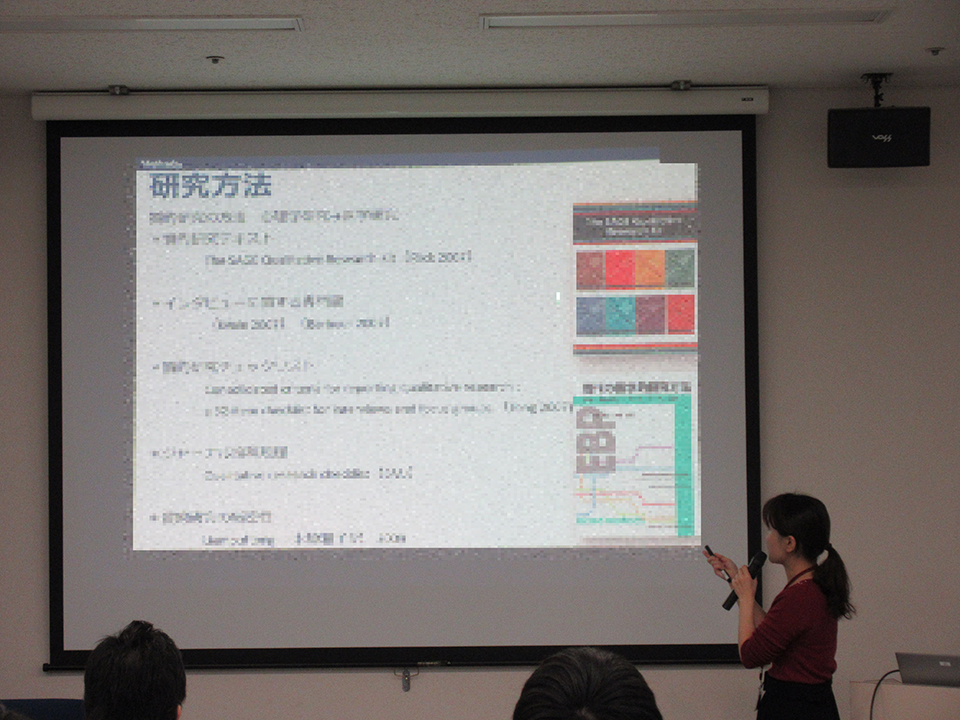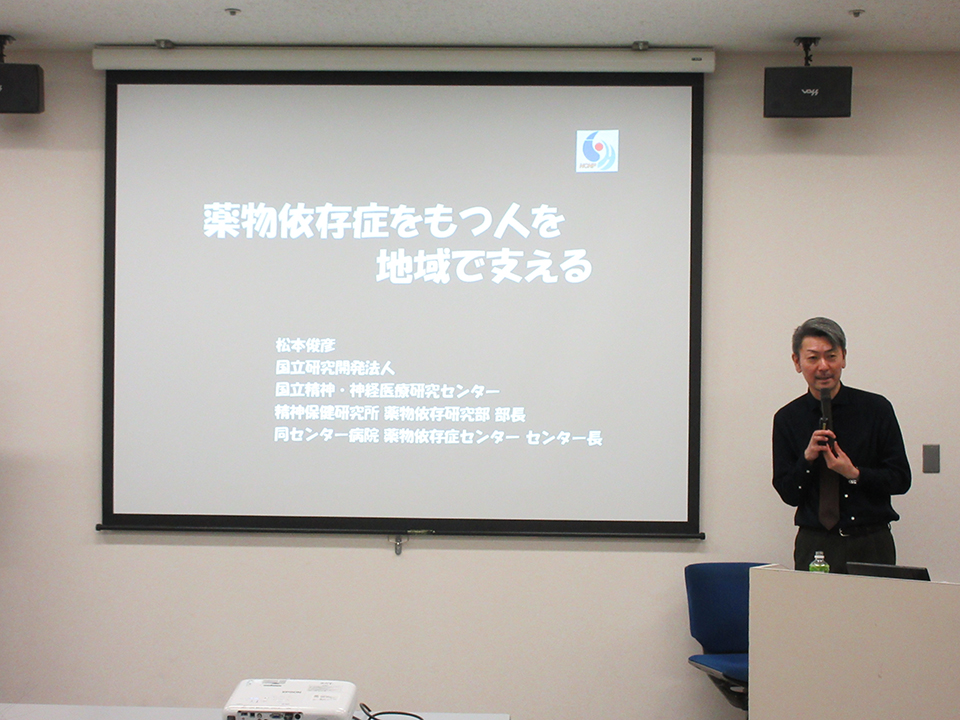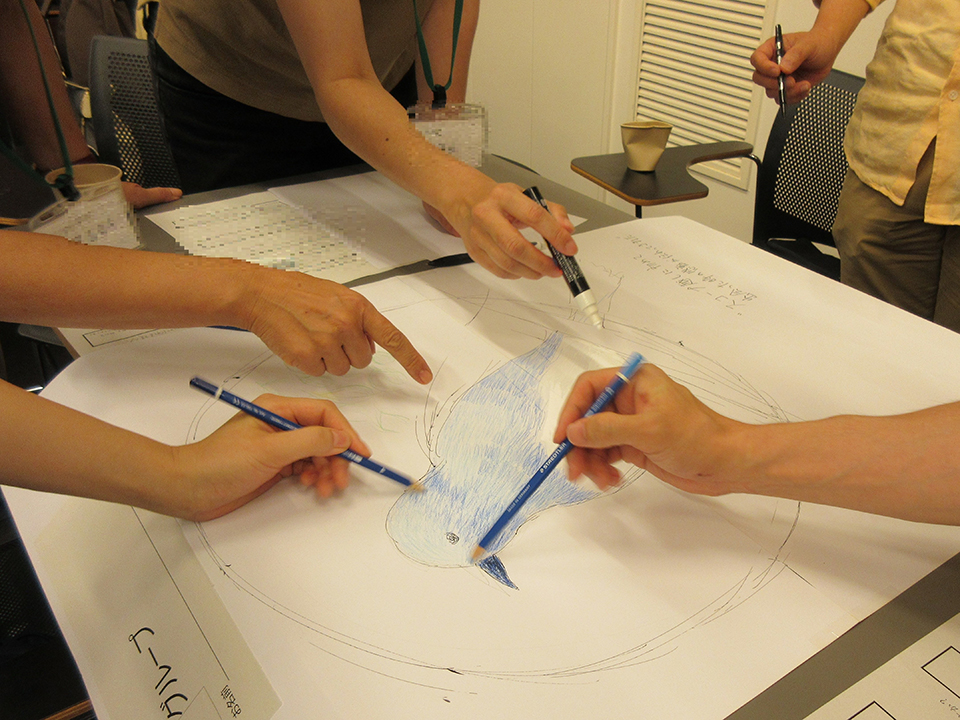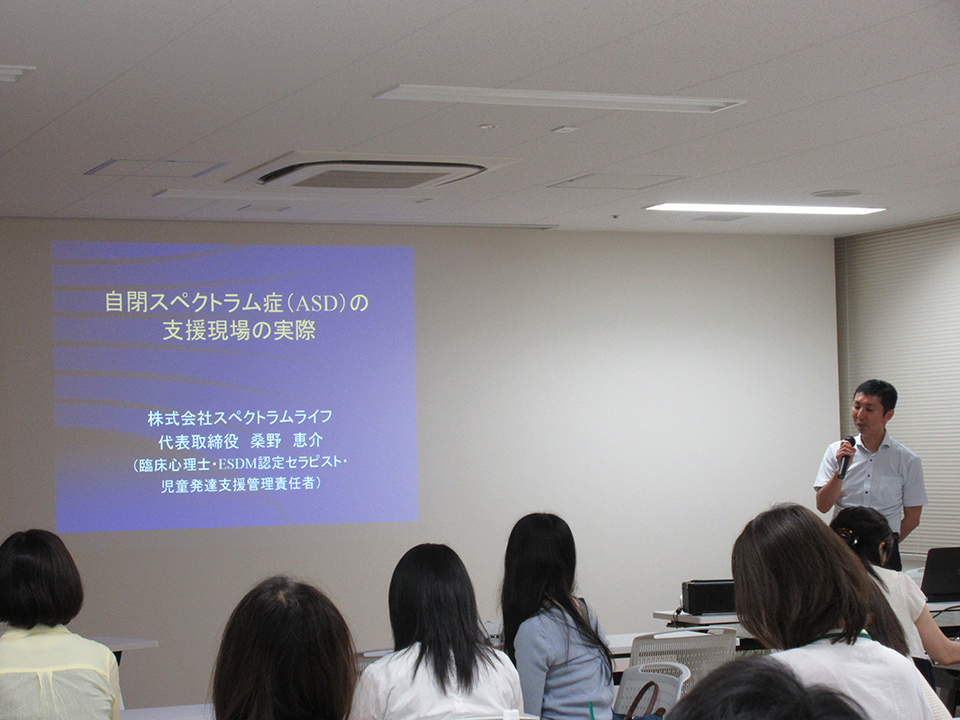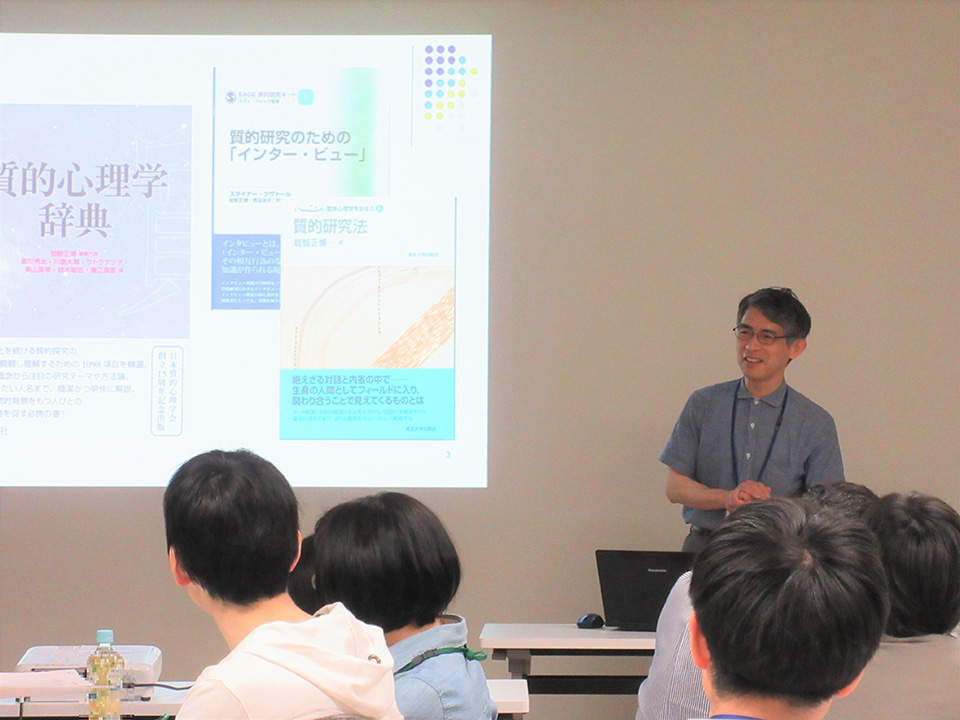養成コースC 職域・地域架橋型コーディネーター
Cコース合同 2月活動報告
- 日時
- 2022年2月19日(土)
2022年2月20(日)
- 方法
- オンライン会議システムによる開催
概要
養成コースC 職域・地域架橋型コーディネーター Cコース合同の2月講義が開催されました。
2月19日午前は、笠井さつき帝京大学心理臨床センター教授から「精神分析的心理療法における『女性であること』とトラウマ」についてご講義いただきました。具体的な臨床実践をご紹介いただきながら、精神分析的心理療法とトラウマ、そして“母親という主体”についてご解説いただき、トラウマインフォームドな支援の手がかりとなる考え方や姿勢を学ぶことができました。
午後は、松本俊彦国立精神・神経医療研究センター部長から「薬物依存症をもつ人を地域で支える」についてご講義いただきました。調査研究や支援の実際と結びつけながら歴史的、文化的、社会的視点から薬物依存症についてお話しいただき、個人の病理や責任という枠を超えて理解することや繋がる支援を考えていく必要性を学びました。
2月20日午前は、澁谷智子成蹊大学文学部現代社会学科教授から「ヤングケアラー」について社会学の立場から背景要因や実態、支援に至るまで幅広くお話いただきました。当事者の語りや海外での支援モデルなどもご紹介いただき、子どもの権利や緩むことのできる仕組みづくりについて再考する機会となりました。
午後は、上野千鶴子認定NPO 法人ウィメンズアクションネットワーク理事長から「ミソジニー・性暴力・フェミサイド」というテーマで、社会の中の性にまつわる概念について理論と実践の両面から詳しくご解説いただきました。歴史文化的構造を捉え、連続性や関係性に目を向けながら現象を理解しようとする視点は、対人支援の在り方に深く通ずるところがありました。
受講生の感想
(笠井先生の講義)
患者さんやそのご家族と話す際には、自分が誰の視点で見て、考えているのか、患者さんの”家族” ”保護者” ”母親”ではなく、一人の主体性をもった人として会っているのだということを意識していきたいと思いました。
(松本先生の講義)
薬物や自傷などによりむしろ生き延びてきた「安心して人に依存できない」病理を抱える人たちに対して何が真に有効な支援なのか、視点を大きく変える必要性を強く感じさせられました。
(澁谷先生の講義)
ヤングケアラーの実態について、統計的な資料とナラティブの両方から知ることができました。「ヤングケアラー」という概念・言葉ができることで切り取ることのできる現象があり、社会学的な視点から生まれた言葉が支援にもつながるプロセスがあるとわかりました。
(上野先生の講義)
意識的にも無意識にも自分が加害者になっている可能性があることに気がつき、とても胸が苦しくなりました。被害や加害に関して普段どれだけ見ないようにしているか、社会や自分を変える機会をどれだけ逃してきたのかということに愕然としています。些細なことに敏感に感じとり、考え、声に出していけるようになりたいと思いました。
C-1 職域架橋型コース 1月活動報告
- 日時
- 2022年1月8日(土)
2022年1月9日(日)
- 方法
- オンライン会議システムによる開催
概要
養成コースC 職域・地域架橋型コーディネーター C-1職域架橋型コースの1月講義が開催されました。
1月8日午前は、新井英靖茨城大学教育学部教授から「学校領域における多職種連携~教育と医療の立場の違いを超えた協働のあり方~」について、具体的な相談場面を想定したアプローチも含めてお話いただきました。学校教師の文化的側面や教育の立場から他専門職がどのように捉えられる傾向にあるか等の視点を学び、互いの専門性や背景を理解する大切さを再認識することができました。
午後は、中原睦美鹿児島大学大学院臨床心理学研究科研究科長/教授から「コラージュ療法の理論と実践~コラージュ・ボックス法を中心に~」というテーマでご講義いただきました。受講生それぞれがコラージュ制作を体験し、感じること、表現することに集中した貴重な時間となりました。また、ボックス法について学校領域での臨床を中心に実践をご紹介いただき、コラージュ療法の手続きや適用性、クライエントに向き合う姿勢を学びました。
1月9日午前は、藤森麻衣子国立研究開発法人国立がん研究センター室長から「オンコロジー領域の心理社会支援」と題して、研究データやモデルを示しながらサイコオンコロジーの知見をご紹介いただきました。グループワークでは、架空の状況における患者や家族とのコミュニケーションの取り方について意見交換を行い、がん医療における心理社会的支援の必要性への理解を深めることができました。
午後は、能智正博東京大学大学院教育学研究科教授から「質的研究入門~ナラティヴの重要性~」について、お話いただきました。質的研究の概観に加え、ナラティヴの意味や構造、その捉え方について詳しくご解説いただきました。その後、個人ワークではインタビューのサンプルデータを読む体験を行い、質的研究の視点や語りの奥深さと多様性を感じることができました。
受講生の感想
(新井先生の講義)
学校の先生が大事にしている「価値」を解説していただき、普段の関わりのなかでの疑問が解けました。違いに自覚的になり、その人を理解しようとしながら連携していきたいと思います。
(中原先生の講義)
画用紙が届いた段階から何が始まるのだろう?と大変ワクワクしながら講義を受けることが出来ました。遠隔ではありましたが、先生や受講生の皆様と同じ時間を共有し、作品を作っていく時間は純粋に楽しく、思い出深い体験となりました。
(藤森先生の講義)
各々の気持ちを適切に理解した上での相互のコミュニケーションがいかに大切であるか、そして生きる力にも大きく影響をもたらすものなのか、強く伝わってきました。当事者・家族にとって悲嘆のある状況も含めての支援では、よりコミュニケーションが保障されるべきと感じました。
(能智先生の講義)
ナラティヴは自然とその方から出てくるものという印象を持っていました。しかし、インタビュアーが求めていること、対象者の自己呈示にとどまらず、社会、文化的な力もナラティヴを生み出す力に影響していることを新たに学ぶことができました。
第4回公開シンポジウム 活動報告
- 日時
- 2021年12月20日(月)~2022年1月4日(火)
- 方法
- 特設サイトにて期間中オンデマンド配信(要申込)
プログラム
当事者中心の時代の専門性
~対人支援の倫理的転回に向けた内なる対話~
趣旨説明
笠井清登(東京大学大学院医学系研究科教授)
精神分析の訓練と文化の問題
富樫公一(甲南大学文学部 教授)
心が消えゆく時代の心の専門家
東畑開人(十文字学園女子大学 教育人文学部 心理学科 准教授)
写真で伝える被災地・紛争地の声、 そしてルーツをめぐる旅
安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
対談:~中動態と当事者研究~
國分功一郎(東京大学大学院総合文化研究科 准教授)
熊谷晋一郎(東京大学先端科学技術研究センター 准教授)
パネルディスカッション
富樫公一/東畑開人/安田菜津紀/國分功一郎/熊谷晋一郎
司会:熊倉陽介/笠井さつき
概要
文部科学省課題解決型高度医療人材養成プログラム 東京大学 職域・地域架橋型価値に基づく支援者育成 第4回公開シンポジウム「当事者中心の時代の専門性~対人支援の倫理的転回に向けた内なる対話~」が開催されました。今年度は特設サイトを立ち上げ、期間中オンデマンド配信による開催としたことで1277名から申込みをいただき、例年以上にたくさんの皆様にご視聴いただくことができました。
はじめに、笠井清登東京大学大学院医学系研究科教授よりTICPOC及び本シンポジウムの趣旨について説明がありました。その後、富樫公一甲南大学文学部教授から「精神分析の訓練と文化の問題」について、東畑開人十文字学園女子大学教育人文学部心理学科准教授から「心が消えゆく時代の心の専門家」についてお話いただきました。また、フォトジャーナリストの安田菜津紀さんから「写真で伝える被災地・紛争地の声、そしてルーツをめぐる旅」というテーマでご講演いただきました。その後、「~中動態と当事者研究~」について國分功一郎東京大学大学院総合文化研究科准教授と熊谷晋一郎東京大学先端科学技術研究センター准教授による対談、パネリスト全員によるディスカッションが行われました。一日を通して、自己と他者の境界や社会・歴史的文脈を踏まえた人間観及び倫理観について考えさせられる貴重な機会となりました。
C-2 地域連携型コース 12月活動報告
- 日時
- 2021年12月11日(土)
2021年12月12日(日)
- 方法
- オンライン会議システムによる開催
概要
養成コースC 職域・地域架橋型コーディネーター C-2地域連携型コースの12月講義が開催されました。
12月11日午前は、北中淳子慶應義塾大学文学部・大学院社会学研究科教授から「医療人類学の基本と最前線」について、うつ病に焦点を当ててお話しいただきました。ひとつの病が社会的・文化的・歴史的にどのように構成されているか医療人類学の視点から眺めてみることで、改めて精神医学は不確実性を有していることや多様な説明モデルを有していることを学びました。
午後は、大塚耕太郎岩手医科大学神経精神科学講座教授から「東日本大震災後のメンタルヘルス対策」についてお話しいただきました。被災地支援のみならず、自殺予防対策プログラムや日頃からの地域のメンタルヘルス問題への取り組みのお話を通して、医療・保健・福祉・生活支援等、地域全体の体制を知り連携していく大切さや長期化を想定した支援の方法論、支援者としての基本姿勢を学びました。
12月12日午前は、鶴田信子被害者支援都民センター心理相談担当責任者より「事件・事故の被害者支援」について、都民センターの機能のご紹介から被害者支援の歴史や法制度、トラウマインフォームドケアの視点まで幅広くご講義いただきました。グループワークでは、架空の状況に対して多様な立場でできる関わりを考え意見交換をしました。誰もが被害者支援に関わる可能性があること、また遠巻きにせず関わることが求められていることを再認識することができました。
午後は、水流聡子東京大学総括プロジェクト機構『QualityとHealthを基盤におくサービスエクセレンス社会システム工学』総括寄付講座特任教授から「対人支援サービスの質の評価とPDCAサイクル」についてお話いただきました。概念モデルやデータを用いながら品質管理工学の知見をお示しいただき、質の評価が難しい対人支援の領域においても構造化や標準化、効率化を目指す視点を取り入れることの意義と基本的な考え方を学びました。
受講生の感想
(北中先生の講義)
うつ病がどのように医療化されていったのかについての学びを通して、今まで考えたことのなかったスケールの構造の中で、医療、文化、経済など様々な相互作用が起きていることを知りました。視界が広がるきっかけを頂いたように思います。
(大塚先生の講義)
震災前から自殺予防対策として地域で取り組んできた活動が、震災時のこころのケア、そしてコロナ禍の対策へと繋がっていること、日頃からのネットワーク作りが大切であるということを学びました。
(鶴田先生の講義)
被害者支援の活動を通してトラウマインフォームドケアが実際にどのように行われているか、そして私たちができることは何かを学ぶ機会となりました。支援にあたり、被害者に起こりうるのが精神・身体的問題と考えてしまいがちでしたが、それだけではなく生活環境や司法手続き上の問題や二次被害といった、事件後の現実の中で生きることに伴う問題に配慮しながら、それぞれの立場や職場でできる支援を考えていきたいです。
(水流先生の講義)
「質の評価」が難しい対人援助の分野においても、用語の定義を押さえ、カテゴリー化し、必要なデータを蓄積することで、最低限を担保する質の均霑化や、省思考・スリム化による対人/エクセレントサービスへの注力など、今後の業務に活かしたい大変示唆に富んだお話でした。
C-1 職域架橋型コース 11月活動報告
- 日時
- 2021年11月20日(土)
2021年11月21日(日)
- 方法
- オンライン会議システムによる開催
概要
養成コースC 職域・地域架橋型コーディネーター C-1職域架橋型コースの11月講義が開催されました。
11月20日午前は、金生由紀子東京大学大学院医学系研究科准教授から「発達障害の臨床」というタイトルで、障害の概念や歴史から臨床のご経験を踏まえた治療・支援の視点に至るまで幅広くお話いただきました。また、成長に伴う状態像の変化や症状の多様性、併発症状などについてもご説明いただき、基本的な認識をもった上でクライエント一人ひとりにアプローチしていく大切さを改めて確認することができました。
午後は、黒田美保帝京大学文学部心理学科教授から「発達障害のアセスメント」についてご講義いただきました。ADOS-2やADI-Rなど自閉スペクトラム症に特化したアセスメントを詳細にご紹介いただくとともに、モデル映像を用いて働きかけや行動観察など日々の臨床にも活きるインフォーマルアセスメントの視点を学ばせていただきました。
11月21日午前は、中村紀子中村心理療法研究室/治療的アセスメント・アジアパシフィックセンター臨床心理士から「見えない心を可視化する~心理アセスメントによるケース理解~」というタイトルでご講義いただきました。協働的/治療的なアセスメントの実際について、臨床実践のお話を通して具体的なプロセスをご紹介いただきました。心理検査は、患者さんが自己理解を深めよりよく生きていくために役に立つものであり、活用によって非常に治療的に機能することを学ぶことができました。
午後は、藤山直樹上智大学総合人間科学部心理学科名誉教授から「精神分析を生きる、そして生かす」というタイトルで、 精神分析家としての生き方や“精神分析とは何か”についてご講演いただきました。実践のお話から日常生活での人間関係とは異なる精神分析という特殊な営みの中での人間関係やその臨床に触れ、精神分析の世界を垣間見させていただく貴重な機会となりました。立場や職種を超えて、精神分析の概念をもつことや支援者自身が精神分析を経験することが一般的な臨床においても有用であることを学ぶことができました。
受講生の感想
(金生先生の講義)
ASDやADHD、チックの症状やそれぞれについて併発症、神経学的な説明や薬物療法まで多岐にわたって「発達障害」を学ぶ貴重な機会を得ることができました。
(黒田先生の講義)
“知能検査でわかる困っていること≠発達障害の症状で困っていること”に自覚的にならなければいけないと再確認しました。ADOS-2やADI-Rなども学んでいきたいです。
(中村先生の講義)
テストの解釈や面接スキル、クライエントさんと共同創造する姿勢などがあってこその協働的/治療的アセスメントだと感じました。心理検査結果からまさに“見えない心が可視化”され、検査を通して心が見つめられたことに感動を覚えました。
(藤山先生の講義)
きれいごとではなく、真剣に二人の間に起こっていることを扱う姿勢を学ぶことができました。精神分析的な見方を身に着けて、日々の臨床に生かせるように精進したいと思いました。
職域・地域架橋型外部実習 活動報告
- 日時
- 2021年10月31日(日)
- 方法
- オンライン会議システムによる開催
概要
職域・地域架橋型外部実習が開催されました。
午前は、TICPOC受講生から「支援の現場から考えるTICPOC」として、それぞれの現場で日々感じている課題意識や葛藤、組織変革に向けた取り組みなどを発表してもらいました。
午後一つ目のセッションでは、昨年に引き続きオンラインで富士癒しの森と中継を繋ぎ、「森の文化祭」の演奏会の音楽、焚火、自然を味わいました。
二つ目のセッションでは、「入院患者さんの権利擁護と治療・医療の狭間で抱えた葛藤の共有と向き合い方の検討」というテーマで、医師や看護師から話題提供した後、グループに分かれて架空の状況をもとに“スタッフとしてどう対応したいか”“患者さんの立場でどう対応してほしいか”意見交換を行いました。多職種で意見を出し合うことで、それぞれの視点や役割について理解を深める機会となったとともに、職種の垣根を越えて、似たような葛藤を抱えている部分についても共有することができました。
最後に、当院のピアサポートワーカーから「リカバリーストーリー」をお話いただき閉会しました。
受講生の感想
(富士癒しの森との中継への感想)
まきを燃やす煙、雨の音、樹木の葉、すばらしい歌声と演奏、さぞかし澄み切った空気なんだろうな、とオンラインながら、自然の良さを満喫いたしました。
(午後のグループワークへの感想)
他職種の方々と架空の状況に対して話し合うことで、視点の持ち方や、ケース理解の仕方が異なることを体験できましたし、それが自分にはない視点で新鮮に思いました。モヤモヤを解消するのではなく、抱えながら自身の実践を振り返る姿勢の大切さを教えていただきました。
(リカバリーストーリーへの感想)
ご自身が経験してきたことを前向きに捉えていらっしゃり、率直に「すごい」と感じた。貴重なリカバリーストーリーをお聴きする機会をいただき、自分の中にある価値観のようなものが触発される感覚があった。
養成コースC 職域・地域架橋型コーディネーター
C-2 地域連携型コース 10月活動報告
- 日時
- 2021年10月2日(土)
2021年10月3日(日)
- 方法
- オンライン会議システムによる開催
概要
養成コースC 職域・地域架橋型コーディネーター C-2地域連携型コースの10月講義が開催されました。
10月2日午前は、三宅和彦文京区子ども家庭支援センター主査から、「文京区の虐待対策と子ども家庭支援」についてお話いただきました。子ども家庭支援センター、児童相談所、要保護児童対策地域協議会のそれぞれの役割や具体的な虐待対応の流れについてご紹介いただきました。その後、虐待に関わる臨床や家庭支援、他機関連携において受講生が日々感じている課題意識や意見を交流し理解を深めました。
午後は、佐々木理恵東京大学医学部附属病院シニアピアサポートワーカーから「リカバリー志向実践のひとつとして」というタイトルで、リカバリーの概念やピアサポートの定義、TICPOC Dコースの実践など幅広くお話いただきました。また、宮本有紀東京大学大学院医学系研究科准教授から「ピアサポートワーカーとコ・プロダクション」と題して、事例をもとに共同創造の理念や取り組みをご紹介いただきました。後半は、フィッシュボウルの手法を用いて受講生参加型で対話が展開され、ピアサポートワーカーと共に働いた経験や専門職・当事者それぞれの立場で大切にしようとしていることについて語られました。
10月3日午前は、夏堀龍暢祐ホームクリニック吾妻橋院長から「地域精神医療のプリンシプル」というタイトルで、医療倫理や意思決定支援の概念からコロナ禍における在宅診療の状況まで、多岐にわたるお話をいただきました。また、架空事例を用いてグループワークを行い、専門職同士の連携(チーム支援)の実践に求められる姿勢や考え方を学びました。
午後は、石井綾華NPO 法人Light Ring.代表理事から「学校メンタルヘルスと若者の自殺対策」についてお話いただきました。若者の自殺対策やLight Ring.のアプローチの概要を紹介いただき、支え手のケアや支援者自身のセルフケアについて考える機会となりました。後半は、ゲートキーパー講座ringsのワークを部分的に体験し、自身の問題解決タイプに合わせた対応法や話の聴き方のポイント、リラックス法を学びました。
受講生の感想
(三宅先生の講義)
大切なことは、それぞれ持っている情報を出し合い、役割を確認し、今後自分の立場でできることを話し合うことだと実感しました。今回、三宅先生のお話を聞いて、児童福祉の法的なことや虐待への介入について知ることができました。
(佐々木さん、宮本先生の講義)
日本のピアサポートワーカーの現状を学び、専門職は専門知を防衛とせず、人間対人間として出会っていく覚悟が必要であるように感じた。そのためには、専門職に内在するスティグマに気づいていくことや、専門職自身の当事者性に気づき受け入れていくこと、その上で専門知を活かすことが役割であると感じた。
(夏堀先生の講義)
医療倫理から日々の実践を振り返り、省察的実践の手がかりを教えていただきました。医学的適応、患者の意向、周囲の状況を踏まえた上で、QOLの向上を考えていくことが求められますが、普段の実践では、QOL向上まではなかなか手が回らない部分があること、それはなぜなのかにこれから意識的になりたいと思いました。
(石井先生の講義)
「身近に支援する人を支える」という視点が、制度の狭間でもあり、かつとても実践的であると今日のお話を聞いて気づかされました。その方法も、大学で研修やワークを行うなど、1番届けたい人に最も効果的に伝わる手段を選んでいて意義のある活動だと思いました。
養成コースC 職域・地域架橋型コーディネーター
Cコース合同 9月活動報告
- 日時
- 2021年9月11日(土)
2021年9月12日(日)
- 方法
- オンライン会議システムによる開催
概要
養成コースC 職域・地域架橋型コーディネーター Cコース合同の9月講義が開催されました。
9月11日午前は、榊原英輔東京大学医学部附属病院講師から「これからの『価値』の話をしよう~未来を生き延びるための哲学~」、村井俊哉京都大学大学院医学研究科教授から「精神医学の多元的理解~多職種協働における折衷主義から多元主義へ~」についてご講義いただきました。Values-based practice(以下VBP)の基礎となる考え方からVBPとほかの理論の関係、精神科医療実践における多元性まで幅広くお話いただき、相手と同じ前提条件に立っているとみなさずに対話する姿勢をもつことの大切さを改めて学ぶことができました。
午後は、東畑開人十文字学園女子大学人間生活学部准教授/白金高輪カウンセリングルーム臨床心理士から「臨床心理学の社会論的転回」についてお話いただきました。個々の援助を考えるためには社会論的アセスメントが必要であること、自分と異なる「価値」をもつ人と共同するために人類学や社会学といった人文知の視点が役立つことを学びました。
9月12日午前は、島本禎子杉並家族会/NPO法人あおば福祉会代表から「家族が望む精神科医療と地域社会」について、当事者家族のお立場からお話いただきました。日本の家族会の歴史や精神科医療の実際、家族会に寄せられる多様な相談内容について知り、支援者としての姿勢や地域社会の在り方について考える貴重な機会となりました。
午後は、笠井清登東京大学大学院医学系研究科教授から「22q11.2欠失症候群のある人の統合的支援の必要性」について医学の立場からお話いただいた後、三ツ井幸子22HEART CLUB副代表から「22q11.2欠失症候群~重複する障害を抱えた子どもとその家族の生活~」というタイトルで当事者家族のお立場からご講義いただきました。医療・福祉・教育の垣根を超えた支援の仕組みやコーディネーター役割を担える人材が求められていることを具体的なケースのお話から学ぶことができました。その後、身体・知的・精神の領域をまたがる多疾患併存に対する支援、発達段階に合わせた切れ目ない支援について全体で意見交換を行いました。
受講生の感想
(榊原先生・村井先生の講義)
自分自身がもっている「価値」にも自覚的になること、またそれを相手に提示(対話)することで、相手の「価値」もクリアになってくるのだと改めて考えました。
(東畑先生の講義)
それぞれの価値の下、何をもってその当事者のよい適応となるのか、偏らずに見つめていき、支援方法を探っていきたいと思いました。人文知を広げていくこと、それが直接的でなくても、自身の視野(仕事上だけでなく、人としても)を広げることとなると感じました。
(島本先生の講義)
家族で抱えてしまう一方で、家族で抱えるように社会が強いている側面もあり、専門職としてだけでなく、地域の住民の1人としてこの問題について考え続けていかなければならないと感じました。
(三ツ井先生の講義)
「医療、福祉、教育、就労などについてこうなるといいなと思ったこと」の内容を拝聴し、たくさんの声に心動かされました。自分の立場でできることは何か、今後の取り組みの方向性を考えていきたいと思います。
養成コースC 職域・地域架橋型コーディネーター
C-1 職域架橋型コース 8月活動報告
- 日時
- 2021年8月28日(土)
2021年8月29日(日)
- 方法
- オンライン会議システムによる開催
概要
養成コースC 職域・地域架橋型コーディネーター C-1職域架橋型コースの8月講義が開催されました。
8月28日午前は、毛利伊吹上智大学総合人間科学部准教授から「認知行動療法において問いかけること~ソクラテス式質問の紹介~」というタイトルで、前半は認知行動療法の基礎となる第2世代の理論、後半はソクラテス式質問法についてご講義いただきました。架空事例を用いたブレーンストーミングを通して、体験的に認知行動療法の考え方に触れ、理解を深めることができました。
午後は、若佐美奈子神戸女学院大学人間科学部准教授から「非分析的臨床場面での精神分析的視点」についてご講義いただきました。精神分析的な耳の傾け方について解説いただき、事例検討のグループワークでは、クライエントの心の中にある対象や防衛機制を見立てる視点について学びました。精神分析的視点をアセスメントに応用することによって見えてくるものやそこから考えられるかかわりを具体的に学ぶことができました。
8月29日午前は、伊藤絵美洗足ストレスコーピング・サポートオフィス所長から「スキーマ療法~入門ワークショップ~」というタイトルで、早期不適応的スキーマの解説を中心に、スキーマ療法の治療戦略や導入の注意点、他の心理療法との相違点に至るまで幅広くご講義いただきました。また、安心安全の確保やセルフケアの重要性について、改めて考えるきっかけとなりました。
午後は、松木邦裕京都大学名誉教授から「多職種協働における力動的視点の適応」について、精神力動的視点を治療や治療のためのマネジメント、多職種協働にどのように活かすか、ケースをご紹介いただきながら解説いただきました。ネガティブケイパビリティの概念をはじめとして、目の前の患者さんへのかかわり方やこころの在り方について、明日からの臨床に役立つお話をいただき、支援者としてエンパワメントされる機会となりました。
受講生の感想
(毛利先生の講義)
認知行動療法の歴史的経緯(第2世代・第3世代等)から、実践的な「ソクラテス式質問」の具体的な進め方まで、理論と実践とが一望でき、理解が深まりました。
(若佐先生の講義)
こころという見えないけれどとても大切なものを、自分のこころという見えないものを一生懸命使って見ようとする営みの、尊さと困難さと奥深さを改めて学ばせていただきました。
(伊藤先生の講義)
スキーマが繰り返される学習の中で形成されるというところで、このあたりが複雑性PTSDの方に有効となる部分なのかなと感じました。スキーマ療法の実践はすぐには難しいと思いますが、スキーマに思いを馳せながら接することがトラウマインフォームドケアになるのではないかと一つの方向性を知ることができ勇気づけられました。
(松木先生の講義)
現場で面接をしていると、「分からない」という感覚をもつと不安になったり自信をなくしたりして、どうすればよかったのか答えを出そうとしてしまいます。でも、考え続けることから逃げずに悩み続けることが大切で、難しいけれど、それがこの仕事なのだと感じました。
養成コースC 職域・地域架橋型コーディネーター
C-2 地域連携型コース 7月活動報告
- 日時
- 2021年7月3日(土)
2021年7月4日(日)
- 方法
- オンライン会議システムによる開催
概要
養成コースC 職域・地域架橋型コーディネーター C-2地域連携型コースの7月講義が開催されました。
7月3日午前は、竹島正(一社)自殺予防と自死遺族支援・調査研究研修センター理事/川崎市総合リハビリテーション推進センター所長から「地域共生社会におけるメンタルヘルスの戦略」についてお話いただきました。
心理社会的課題を抱えた人への支援について、調査研究に基づく支援モデルをお示しいただき、これからの自殺予防における地域の重要性についてご教示いただきました。
午後は、髙瀨顕功大正大学社会共生学部専任講師から「地域と共に生きる寺院と『集いの場』」について、お話いただきました。地域や医療など寺院の外で行われる社会問題やこころを扱う活動、寺院を集いの場として行われる地域活動についてご紹介いただきました。コロナ禍で始まった在日外国人への「支縁」活動や地域寺院の社会貢献など最近の実践についても触れていただき宗教のもつ様々な役割や可能性について学ぶことができました。
7月4日午前は、「精神保健の Organizational Change に向けた研究の方法論」という演題で、山口創生国立精神・神経医療研究センター室長、金原明子東京大学医学部附属病院特任助教からお話いただきました。山口先生には、精神科治療の歴史的な文脈から研究の必要性やリカバリーの概念についてご説明いただきました。また、共同意思決定促進ツール『SHARE』についてもご紹介いただきました。金原先生には、実際の研究を例にしながら、研究を始めるポイントや流れについて具体的に解説いただきました。お二方のご講義から、研究と臨床を別のものとせず、つながりをもって捉える視点を学ぶことができました。
午後は、藤井千代国立精神・神経医療研究センター部長から「精神障害にも対応した地域包括ケアと意思決定支援」という演題で、地域包括ケアシステム構築により目指す方向性から精神科の医療倫理まで、多岐にわたってお話いただきました。架空事例を通して、精神科特有の倫理的なジレンマや今後の地域ケアの課題について考える貴重な機会となりました。
受講生の感想
(竹島先生の講義)
危機を介入のタイミングと捉え、個別対応での燃え尽きを防ぎ、切れ目のない支援を生むためにも地域システム化していくことの重要性を学びました。
(髙瀨先生の講義)
中間集団として、公と私を繋ぐ集いの場としての役割としての寺院、スピリチュアルな問いに応答する活動について学び、自分に何ができるのか、考えるきっかけとなりました。
(山口先生の講義)
当時者の権利と利益を守るために研究は必要で、当事者抜きの研究では現場に新しい知見を実装できないことや当事者との共同研究や臨床での研究の必要性を改めて感じました。
(金原先生の講義)
現場で感じる理不尽さや葛藤を種として、研究に展開していく方法について知ることができました。また研究すること自体が、精神保健そのものの課題を組織的に変化させうるきっかけにもなるのだと、エンパワメントされたように思いました。
(藤井先生の講義)
複合的な困難を抱え地域で生活する人の支援の一端で携わる者として、今ある中でできる支援を考えること、これからどうなっていけば良いかを考え続けて何かの行動につなげることをしていきたいと思いました。
養成コースC 職域・地域架橋型コーディネーター
C-1 職域架橋型コース 6月活動報告
- 日時
- 2021年6月12日(土)
2021年6月13日(日)
- 方法
- オンライン会議システムによる開催
概要
養養成コースC 職域・地域架橋型コーディネーター C-1職域架橋型コースの6月講義が開催されました。
6月12日午前は、笠井清登東京大学大学院医学系研究科教授から「人が人を支援するということを再考する」というタイトルで、C-1コースの主眼と対人支援の見えにくい作用点について説明がありました。また、濱田純子東京大学医学部附属病院こころの発達診療部臨床心理士・公認心理師から、年間講義内容の概説と事例を用いながら本コースのねらいについて補足説明をしました。
午後は、津川律子日本大学文理学部心理学科教授から「心理臨床実践と研究の倫理」についてご講義いただきました。事例検討のワークを通して、倫理的なジレンマから目を逸らさず利益とリスクを多角的に見立てることや職場やチームで話し合うことの大切さを学びました。また、研究における倫理についてもお話いただきました。
6月13日午前は、近藤伸介東京大学医学部附属病院特任講師から「総合病院精神医学と多職種協働」というタイトルでご講義いただきました。東京大学医学部附属病院における多職種協働の実践の紹介や総合病院精神科の意義、精神疾患のある人の身体的健康について幅広くお話いただきました。その後、市橋香代東京大学医学部附属病院特任講師から「『からだの病気』を抱えた人への『こころのケア』」と題して、コンサルテーション・リエゾン精神医学の構成や具体的なアプローチについて、理論と実践を臨床に基づいてわかりやすくお話いただきました。
午後は、森田健太郎東京大学医学部附属病院助教から「統合失調症」、里村嘉弘東京大学大学院医学系研究科医学のダイバーシティ教育研究センター准教授から「うつ病」について、当事者の語りやCOVID-19との関連を含む最新の研究知見、トラウマインフォームドケアの観点を盛り込んだお話をいただきました。また、神出誠一郎東京大学医学部附属病院准教授に「精神科薬理学」について、精神科治療学の発展から現在臨床で広く採用されている代表的な疾患に対する薬物療法まで広く解説いただきました。
受講生の感想
(C-1コースの趣旨と概要)
対人支援において、「見えにくい」・「わかったつもりでいる」ことを意識化する大切さを再認しました。また、TICPOCで学ぶことの概観を丁寧にご説明いただいたので、どのような視点で、受講していけばよいかを把握することができました。
(津川先生の講義)
倫理というと固いイメージがあり、とっつきにくさが強かったのですが、今回の講義を通して、意外に身近にあるもので、仕事の中で割といつも考えていることだと気づきました。状況によって、相手との関係性によって、変わっていくものだととらえ、職場でも話し合っていきたいと思います。
(近藤先生の講義)
チームの体制や形、チームの意義や必要性を踏まえてチーム医療について考えていきたいと思いました。精神症状に目が向きやすいのですが、患者様の日常での困りごとにまず目を向けること、解決につなげることの必要性を学ぶことができました。
(市橋先生の講義)
体の病気におけるリエゾンの大切さがよく伝わりました。ブリーフやナラティブなど会話によることの支援が身体への働きかけの大切なツールになるとよく理解できました。まだまだ心理士が活躍できる場があると思いました。
(森田先生の講義)
統合失調症の多彩な症状について体系的に学ぶことができました。当然症状の軽減ないし消失が治療の目的だと思っていましたが、むしろ日常生活に直結する生活技能が十分でないことやセルフスティグマによる副次的な苦悩を最小限にするようなアプローチも重要だということにとても刺激を受けました。さらには病気になったことが成長のチャンスとなり得ることは、心理職としても何かもっとできることがあるのではと、少し希望のようなものを感じました。
(里村先生の講義)
うつ病について疫学的なデータやCOVID-19の社会状況の中での関連性を最初にお示しいただいたことで、社会とも関連づける視点を持ちながら講義を拝聴することができました。双極性障害との鑑別診断の難しさについても理解が深まりました。
(神出先生の講義)
現在の薬剤の説明だけではなく、歴史からご紹介いただき、とても楽しく勉強できた。また歴史を知ることで薬剤の副作用、効果への理解も深まったように感じる。そのため、医師の処方をみて、どのような意図があってその処方にしているのかを考える視点が加わったように感じる。
養成コースC 職域・地域架橋型コーディネーター
C-2 地域連携型コース 5月活動報告
- 日時
- 2021年5月22日(土)
2021年5月23日(日)
- 方法
- オンライン会議システムによる開催
概要
養成コースC 職域・地域架橋型コーディネーター C-2地域連携型コースの5月講義が開催されました。
5月22日午前は、笠井清登東京大学大学院医学系研究科教授から本プロジェクトの目的と核となる概念について詳細な説明がありました。また、熊倉陽介東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野/国立精神・神経医療研究センター薬物依存研究部科研費研究員から、「どうして住まいの支援からはじめる必要があるのか?-ハウジングファースト」をテーマに話題提供をしました。
午後は、熊谷晋一郎東京大学先端科学技術研究センター准教授、上岡陽江ダルク女性ハウス代表、綾屋紗月東京大学先端科学技術研究センター特任講師より「当事者研究」について、歴史と理念から現代における当事者研究の問題意識まで幅広くお話いただきました。また、参加する人たちが一緒に作るための安全な場作りや情報保障など、具体的な実践知を学ぶことができました。
5月23日午前は、國分功一郎東京大学総合文化研究科・教養学部准教授から「責任、帰責性、『自己責任』」と題したご講演をいただきました。中動態について詳しくご説明いただいた後、意志と責任の違いや関連性、社会の中でどのようにこれらの概念が使われているかお話しいただきました。
午後は、亀岡智美兵庫県こころのケアセンター副センター長兼研究部長から「トラウマインフォームドケア」についてお話いただき、トラウマとトラウマインフォームドケアの理論と実践を学びました。また、事例を用いてトラウマインフォームドな対応について検討するワークを小グループに分かれて行いました。
両日ともに、講義後に受講生同士の自己紹介を行い、一年間共に学ぶ仲間がどのような課題意識をもっているか知る機会となりました。
受講生の感想
(C-2コースの趣旨と概要)
対人援助をする中で、自身の無自覚な側面に気づき、向き合っていく大切さと必要性を意識させていただきました。また、パワーの格差が生じる関係性の中で、人としての尊厳性の平等感覚を見失わずにいられるだろうかと、ドキッとしました。
(熊谷先生・上岡先生・綾屋先生の講義)
人生の主役は当事者であるにも関わらず、当事者の真のニーズは何なのかという最も重要なことを忘れてはならないと再確認させていただきました。
(國分先生の講義)
「責任」「意志」「帰責性」が混同され単純化され悪用されていることや、「自己責任」というものへの巧妙なすり替え、そういったものによって生きづらさへと追い立てられている人々に何ができるのか?何がしたいのか?ということを改めて自分に問いながら学びました。
(亀岡先生の講義)
トラウマインフォームドケアの視点や構造をとても分かりやすく伝えていただきありがとうございました。図や事例を通しての説明がとてもよかったです。ワークでもいろいろな立場の方にお話を聞かせていただき、学びが深まりました。「トラウマを抱えているのでは?」の視線を常にもちたいと思います。