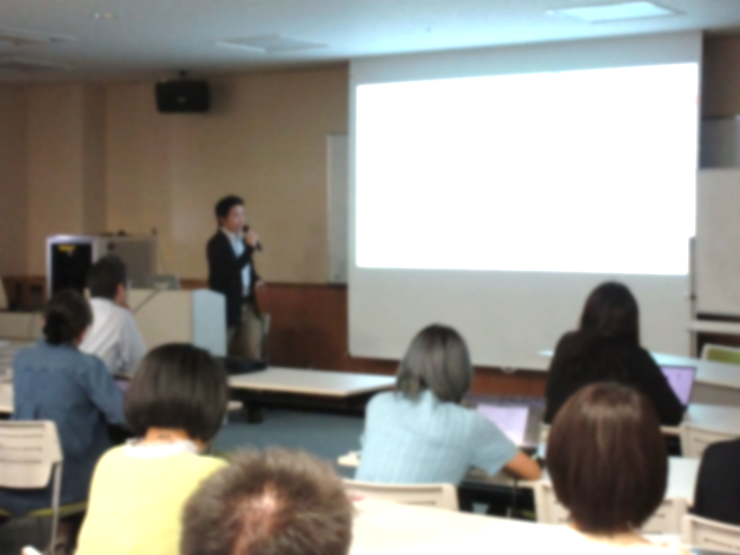Cコース 職域・地域架橋型コーディネーター
C-2地域連携型コース 6月活動報告
- 日時
- 2024年6月16日(日)
- 方法
- 東京大学本郷キャンパスにて対面開催
概要
職域・地域架橋型コーディネーター養成C-2コース 6月講義が開催されました。
6月16日午前被害者支援-TICに基づく支援と支援者支援-
被害者支援都民センター 鶴田信子 心理相談担当責任者
6月16日午後薬物依存症をもつ人を地域で支える
国立精神・神経医療研究センター 松本俊彦 部長
受講生の感想
(鶴田先生の講義)
犯罪被害者の心理的ケアを担う支援のなかで、人と人、人と社会との継続的な結びつき(つながり)が重視されることを改めて理解するとともに、その「つながり」が相手の中で満たされていくことの難しさを痛感した。TICには、被害者のみでなく支援者自身のトラウマのケアも含み、支援をしている自分の状態を俯瞰して「知る」ことや、支援者もまた周囲と「つながる」ことが必要なのだと思った。
(松本先生の講義)
松本先生の講義を対面で受講できることを楽しみにしていました。温かく力強く魅力的な先生のお話に、支援者として多くの気づきとエネルギーをいただきました。アディクションは苦しい今を生きのびるために必要なもの、依存症とは安心して人に依存できない病気など、依存症について理解することは、支援の姿勢に大きく影響すると思いました。『ダメ。ゼッタイ』の風潮やスティグマのある社会の中では、ただでさえ人に依存できない方をますます孤立に追い込んでしまいます。アディクションを即やめさせるのではなく、ハームリダクションしながら人とのつながりを増やすことが回復につながることを、支援者として心に留めていきたいと思います。